 少女マンガをそんなに熱心に読んだ方ではないけれど、好きな作品はある。成田美名子の「エイリアン通り」「CIPHER」はちょうど大学生の頃だったけど、単行本を揃えていた。紡木たくも読んでいたけど、いま確認すると「ホットロード」は、もう社会人になっていたのか。
少女マンガをそんなに熱心に読んだ方ではないけれど、好きな作品はある。成田美名子の「エイリアン通り」「CIPHER」はちょうど大学生の頃だったけど、単行本を揃えていた。紡木たくも読んでいたけど、いま確認すると「ホットロード」は、もう社会人になっていたのか。
他にも「有閑倶楽部」や「スケバン刑事」とか、読んでいたけど共学高校の文化部だったので、周りから借りていたのだと思う。そして、江口寿史を貸していたりしたはずだ。
少女マンガにはその程度の関わりしかなくても、萩尾望都はどこか別格の感じがして、いまでも「ポーの一族」や「トーマの心臓」は文庫が手元にある。
ところが、竹宮恵子は「知っているけど」という感じで、きちんと読んでいなかった。ただ「風と木の詩」のインパクトは相当強かったことを覚えている。
kindle unlimitedの試用中だったこともあり、1巻を読んでみたけれど、相当な息苦しい緊張感がある。流行りものは手を出していたはずなのでけど、この作品は苦手だったのだろう。 >> 少女マンガ史の奇跡「少年の名はジルベール」の続きを読む
 ヒラリーの健康問題は、相当波紋を広げるかもしれない。11日の式典での途中退場は熱中症かもしれないけど、「肺炎だった」ということが後から出てくるのが、どうにもまずい。ただでさえ「嘘つき」のラベルがついて回るだけに、これは波紋を広げるだろう。
ヒラリーの健康問題は、相当波紋を広げるかもしれない。11日の式典での途中退場は熱中症かもしれないけど、「肺炎だった」ということが後から出てくるのが、どうにもまずい。ただでさえ「嘘つき」のラベルがついて回るだけに、これは波紋を広げるだろう。
ただし、トランプも下手な攻撃をすると、また自爆するかもしれない。いずれにしても、史上稀に見る、というかついに米国大統領選挙もここまで来たかと、もう感慨深いくらいだ。
とはいえ、米国大統領選は、まさに「生きたケーススタディ」だ。政治学の選挙研究はもちろん、社会学的に切り口は多い。そして、メディアの仕事をしているものにとっては、貴重なケースの宝庫だ。
大統領選を扱った本は山ほどあるけれど、もしメディアやコミュニケーション、広告などの仕事をしているのならば、この「中傷と陰謀 アメリカ大統領選狂騒史」はぜひ読んでおくといいと思う。大統領選をキャンペーンの歴史から追っているのだけれど、それはまさにメディアの歴史そのものだし、もちろん「いま」を読み解くこともできる。
単に過去を書いているのではなく、理論的な背景も説明してあるので、「コミュニケーション論」の入門にもなり、米国の社会や政治も見えてくるのだ。 >> 大統領選挙はメディア論ケースの宝庫。『中傷と陰謀』の続きを読む
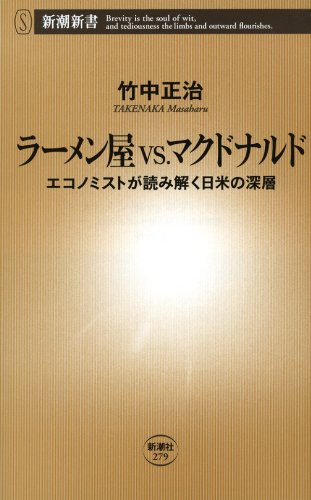 いつ頃からか分からないんだけど、メディアの見出しに、「衝撃」と言う言葉が増えた気がする。今日だったら「LINEモバイルの衝撃」で、「ミサイル3発の衝撃」で、「白鵬休場の衝撃」なのか。ま、休場はさすがに大袈裟か。
いつ頃からか分からないんだけど、メディアの見出しに、「衝撃」と言う言葉が増えた気がする。今日だったら「LINEモバイルの衝撃」で、「ミサイル3発の衝撃」で、「白鵬休場の衝撃」なのか。ま、休場はさすがに大袈裟か。
こういう傾向は、果たして「日本らしい」のか?別にすべての国を調べているわけではないが、少なくても米国との対比では「日本的」と言っていいらしい。
竹中正治氏の「ラーメン屋vs.マクドナルド」(新潮新書)は、2008年9月というリーマンショック真っ只中に刊行されているが、その前年の日米ビジネス誌の見出しを比較している。
そうすると、日本は76%がネガティブだが、米国では56%だったという。金融危機直前だったこともあるが、震源地よりも日本の方がネガティブだ。「危機」「崩壊」などがやたらと多いという分析だ。
この時の日本は、比較的悪くはなかった時期だが、それでも長い間の低迷があってこういう傾向になったのかもしれない。
さらに日本の首相が使う言葉についても、所信表明演説の調査をもとに「課題」「努力」などが多いという。一方で、大統領は夢を語ることが多い。
そして「危機感駆動型」の日本と、「希望駆動型」という分析をしている。
日本と米国を比較して論じることは、よくなされてきた。一方で「外国では~」という戦後の比較文化論のほとんどが、米国をはじめとする欧米だったことへの批判も強く、さらに多元的な分析がおこなわるようになった。 >> 「崩壊危機の衝撃の真実」の衝撃。の続きを読む
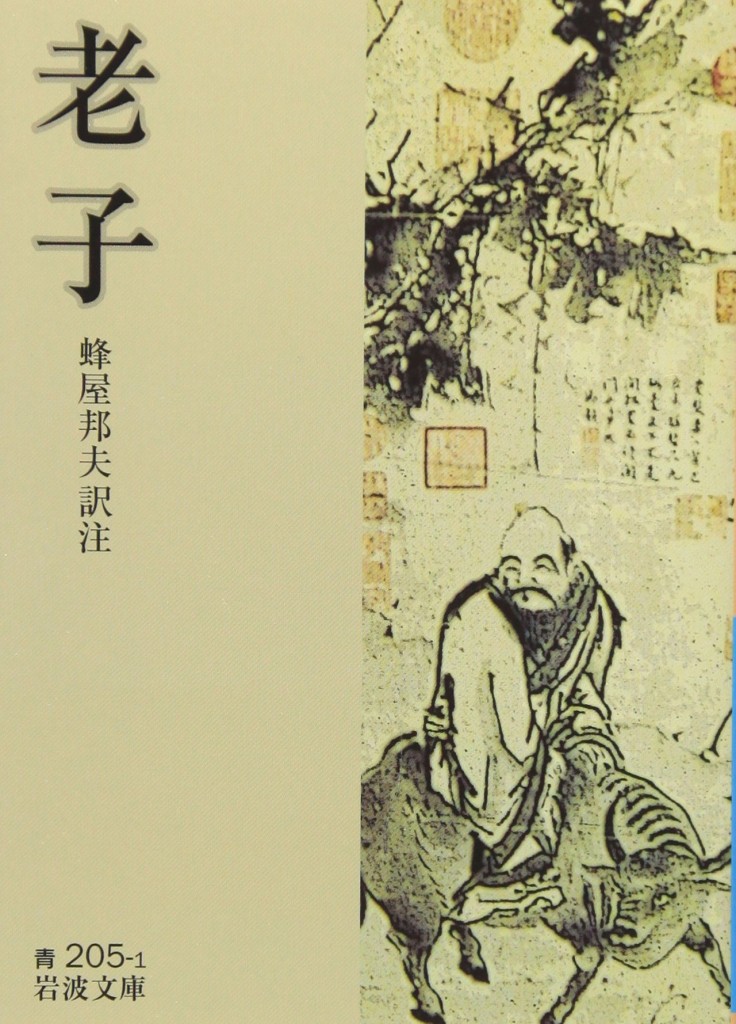 昨日近所の店で1人でランチをしていたら、隣の客が夏の終わりを嘆いていた。
昨日近所の店で1人でランチをしていたら、隣の客が夏の終わりを嘆いていた。
女性2人なのだが、「もう30日なのに」とため息気味だ。しようと思ったことは殆どできず、本棚の整理がやっとだという。もう1人も相槌を打ちつつ、9月からに備えようかと励まし合っていた。
途中でわかったのだが、地元の中学校の先生だった。そうか、生徒が焦っている頃、先生も嘆いてる。なあんだ、「夏休みの宿題」やっていないんだ、と生徒が聞いたら喜ぶだろうな。
いずれにせよ、こうした夏の終わりの寂しい時は、ゆるゆると気を持ち直すしかない。晩夏に限らず、そういう変わり目の季節は「老子」が何とも沁みてくる。沁みる、というと単にしみじみするだけのようだが、老子にはそれなりの不思議なエネルギーがあって、読み返してしまう。
さて、夏には遠出した人も多いだろうが、そうもいかなかった人もいるだろう。いろんな旅する人の話を聞いて思うのだけど、「旅の数や距離と、本人の知恵や見識はあまり関係ない」ということだ。
学生の頃は違った。「1人で世界一周」みたいな経験はそれだけで凄いんだなと思ってた。ただ、段々と「だから、何なんだろう」と思うようになってきた。
ひところは、就職活動で「旅の経験」を語る学生が多かった。世界一周はさすがに少ないだろうが、米国やユーラシア横断などだと、たしかに「語れるネタ」ではある。だから「僕は海外行ったことなくて」という不安を訴える学生もいた。 >> 世界を見たからといって、世界がわかるとは限らない。の続きを読む
ロシア革命の時の、英国情報部を巡る歴史ノンフィクションなのだけれど、当時の緊迫感がジワジワ伝わってくるだけでなく、現在にいたる「ややこしさ」のルーツもまた見えてくる。
英国の秘密情報部は、MI6あるいはSISなどの略称でも知られる。フィクションでも有名人を輩出していて、もっとも知られるのは007のジェームス・ボンド。その次が、ジャック・バンコランだろう。(多分)
英国は「七つの海を支配した」歴史を持ち、米国と相まって英語の影響力も強い。グローバルな大国だが、どこか「世界を背負ってる」感じがする。007は英国を守るというより、世界を助けるという感じだし、サンダーバードも「国際救助隊」だ。
その理由が、また何となくわかってくるのがこの本の面白いところだ。
組織の発足は、第一次世界大戦がきっかけになっている。ただし、この時代は共産主義の風、どころか嵐が吹き荒れて大戦末期にはロシア革命が起きた。
情報部の活動は、勢いレーニンのソ連をマークすることになる。と書きたいところだが、ソ連の成立前にまずは「ボルシェビキ」が英国の敵となったわけだ。そういえば、もう、ボルシェビキとか、言葉自体が懐かしい。コルホーズとかソホーズとか、昔の社会科はロシア語を暗記させていたんだよな。
さて、この本は基本的には英国側の視点で書かれる。そして、英国がなぜレーニンを警戒していたのか?それは、レーニンが「世界革命」を唱えていたことも理由だが、もう一つ重要な理由があった。
インドである。これは、不勉強だったなぁと思った。インドの独立勢力に呼応するようにして、レーニン率いるボルシェビキは、その活動を支援しようとした。そうなると、諜報戦の舞台は中央アジアとなり、アフガニスタンあらタジキスタン辺りが鍵を握ることになる。
前半の舞台は、ペテルブルクからモスクワへの潜入が中心だが、後半はユーラシアのまん真ん中となる。そして通信手段が未発達な時代だからこそ「人」を巡る話がとてもスリリングになる。
そう思うと、007がエキゾチックな舞台で切った張ったをやっているのもよくわかる。インドとレーニンの握手は、当時の英国にとっては悪夢だし、あの辺りは英国情報部にとっては大切な庭なのである。現地にとっては、たまったものではないが。
そして、ソ連は79年にアフガニスタンに侵攻し、モスクワオリンピックは大騒動になって、そこから10年ほどで国が崩壊した。その後のアフガニスタンは安定を欠き、英国は深く関与していることの理由も、この時代に遡るわけだ。
ちなみに、この頃のチャーチルは、どうも今一つ判断能力が良くないように思えるんだけど、彼はいつ頃「化けた」のだろうか。それとも、そもそもそういう人だったのか。そのあたりも、また気になってくる。









