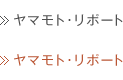COVID-19のワクチン接種がいち早く進んだ国の1つがイスラエルだった。これは国全体が「臨戦態勢」にあるのだろうな、と感じたけどやはり軍が前面に出て進めたようだ。
COVID-19のワクチン接種がいち早く進んだ国の1つがイスラエルだった。これは国全体が「臨戦態勢」にあるのだろうな、と感じたけどやはり軍が前面に出て進めたようだ。
最近では先端技術の分野でも注目されるが、その背景もまた同様だろう。ちなみに作戦遂行のために重要な「ドローン」は90年代から登場していることも本書でわかる。
それにしても、この本のタイトルはちょっと矛盾しているようにも思う。「暗殺」でありながら、それが「全史」となるのであれば、それは周知の事実ということになる。
読んでいけばわかるのだけれど、暗殺というのは、全面的戦闘の代替手法としての、治安・軍事作戦と位置付けられている。そして、この本は「暗殺史」のようでありながら、戦後中東史をクッキリと浮き上がらせているのだ。
日本にとって、というか少なくても自分にとって中東の政治事情というのはどうしても「飲み込めきれない」感じがある。頭で理解していても、感覚的に遠い。子どもの頃にオイルショックがあり、その流れで教わった時も、先生が「これは難しい問題だ」と言っていたのを覚えている。
その後もカーターやクリントンによる仲介は知っているし、ガザ地区やゴラン高原、ヨルダン川西岸という単語もニュースでは山ほど耳にしているけど、その意味合いはどこかぼんやりしていた。
そういう中で、この本は裏から歴史をあぶりだしていくことで、表で起きていることが段々と理解できていくように書かれている。出てくる登場人物や事件などを検索しながら読むので時間はかかるのだけれど、それだけの価値はあると思う。
それでも、読んだ結果としては、やはり「難しい問題だ」としか言いようがない。
上巻はPLOが台頭する中での「組織対組織」の戦いという感じがするけれど、下巻でヒズボラやハマスが出てくると様相が変わってくる。彼らの自爆テロはイスラエルの人々を恐怖に陥れ、出口の見えない状況になっていく。
そして、それぞれの側で呆然とするくらい「普通の人々」の命が失われていることがわかる。
筆者はイスラエル最大の日刊紙の特派員である。冒頭で自分のことを「情報機関の行動に対して批判的だった」と書いているが、全体の筆致としては歴史を中立的に書こうとしていて、煽情的ではない。
だからこそ、歴史が浮き上がってくるように読めるのだ。
最終章のタイトル「みごとな戦術的成功、悲惨な戦略的失敗」は、この暗殺史を象徴している言葉かもしれない。個別のオペレーションがうまくいくほど、長期的には外交的失敗から国益の損失につながることもまた多いのだ。
戦後の中東で何が起きていたのか?を改めて知るための本としてお薦めできる。「難しい問題だ」ということと再確認するのもわるくない。
 「無限」という概念は、ちょっと考えると気が遠くなり、さらに考えると頭がクラクラする。もう、それが文系脳の限界だと思っていた、、だから、このタイトルを見ると、もうそれだけで不安になるんだけれど、物理学者である著者もその辺りはちゃんとわかっているようで、第一章は「気が遠くなる大きさ」となっていて、ちょっとホッとする。
「無限」という概念は、ちょっと考えると気が遠くなり、さらに考えると頭がクラクラする。もう、それが文系脳の限界だと思っていた、、だから、このタイトルを見ると、もうそれだけで不安になるんだけれど、物理学者である著者もその辺りはちゃんとわかっているようで、第一章は「気が遠くなる大きさ」となっていて、ちょっとホッとする。
そして、「無限の本当の意味を考えると頭がクラクラするような結論に導かれる」と書かれていて、多分この「クラクラ」は僕のクラクラとは水準が違うような気がするのだけれど、このタイトルの問いは、それくらいの難題だということだろう。
完全に内容を理解しないで評するのも変だとは思いつつ書いているんだけど、この本は「無限」という概念との付き合い方やその歴史が述べられていて、それがとても興味深いのだ。そして「無限」の概念の扱い方が物理学と数学で異なることも、初めて知った。
「数学の世界では別だが、物理学では普通無限大というものを有限の数が大きくなっった極限として扱う」ということなのだ。その後の説明にあるように、たしかに物理学は測定できる数値を求めるのだから無限の扱い方が数学とは異なる。
一方で、数学的な実無限という視点だと、別の議論が起きてくる。たとえば「自然数全体の集合」と、「整数全体の集合」を比べてその要素の数はどちらが大きいか?というテーマが出てくる。
整数はゼロも負の数も含まれるので、「一見すると整数全体の方が自然数全体よりも多そうだ」ということになりそうだけど、そうはいかない。 >> 【書評】『宇宙は無限か有限か』というクラクラする話。の続きを読む
 昨年夏に出た本なんだけど、タイラー・コーエンの『大分断』は、現代が”The Complacent Class”で、これはサブタイトルのように「現状満足階級」という意味だ。この本では、こうした階層が米国で増加して、その結果過去に比べて「おとなしく」なっていて、実は起業も減り、移住や転職も少なくなり、暴動も減って、つまり全体として「おとなしく」なったことへの危惧が論じられている。
昨年夏に出た本なんだけど、タイラー・コーエンの『大分断』は、現代が”The Complacent Class”で、これはサブタイトルのように「現状満足階級」という意味だ。この本では、こうした階層が米国で増加して、その結果過去に比べて「おとなしく」なっていて、実は起業も減り、移住や転職も少なくなり、暴動も減って、つまり全体として「おとなしく」なったことへの危惧が論じられている。
そしてよりダイナミックな社会として中国が比較対象になるわけだけど、じゃあ日本はどうかというと、わざわざ日本語版序文でしっかり言及している。「日本は『現状満足階級』の先駆者だ」と書かれていて、もうこれは褒め殺しかと思ってしまう。
日本の経済的快進撃は止まっても、レストランの水準は上がり、デザインも洗練されたという。アッと思ったのは「クラシック音楽愛好家のレベルの高さでも日本に勝る国はそうない」という記述だ。おそらく筆者は日本に来てコンサートを聴く機会でもあったのだろうが、これは来日演奏家が世辞ではなく言うこともある。
まあ、褒め殺し感はさらに強まるんだけど、それはそれとして、この本で気になったキーワードの1つが、「カウンターシグナリング」という言葉だ。
説明は、こんな感じ。
「アメリカの富裕層は最近、いわゆる『カウンターシグナリング』により自らの社会的地位をアピールすることが多くなった。カウンターシグナリングとは、『わざわざ社会的地位をアピールするまでもない』ことをアピールする行為のことだ。」 >> 『大分断』の「カウンターシグナリング」という言葉が気になる。の続きを読む
 このタイトルを目にした時、どんな感想を抱くだろうか?悲しみや笑い、あるいは怒りなどの情動は、外からの刺激に対して内から沸き起こり、それはまた、「ある程度」共有できるものと考えるのではないだろうか。
このタイトルを目にした時、どんな感想を抱くだろうか?悲しみや笑い、あるいは怒りなどの情動は、外からの刺激に対して内から沸き起こり、それはまた、「ある程度」共有できるものと考えるのではないだろうか。
芝居や映画を見て、同じようなところで笑い、あるいは涙する。それは海外の作品だったり、数百年前の脚本であったりもする。そういう時に、ついつい人間の情動は時代や国境を越えた普遍性を持っていると思うこともあるだろう。
ところが、注意深く見れば笑いの沸点が低い人もいれば、いつまでもムスッとしている人もいる。悲しい場面でも、全員が泣くわけではない。
いろいろと思い出していけば、そうした情動は実体験や、触れて来た文化などの文脈によって決まっているのではないか?と感じることもある。
本書は、「古典的情動理論」に真っ向から異を唱える。この古典的情動理論は「怖れ・怒り・悲しみなど人間の情動は普遍的である」という考え方だ。その根拠になった実験は、いろいろな表情の顔写真を見せて、その顔写真にもっともふさわしい言葉を単語の選択肢やストーリーと合致させるというものだ。
そこでは、研究発祥の欧米のみではなく世界のさまざまなエリアで実証されたという。
しかし、本当にそうなのか?実は何十年も権威をもってきたこのエクマンの実験については、昨年「日本人には合致しない」という研究結果も発表されている。
そして、そもそもこの古典的情動理論のフレーム自体に異を唱えて、「構成主義的情動理論」を唱えるのが筆者の立場だ。
情動はもともと人に備わっているものではなく、その文化の中で育まれていく。たとえば日本語の「ありがた迷惑」や、ドイツ語の「シャーマンフロイデ」に当たる言葉は英語にはなく、似たような例は世界中にある。
にもかかわらず、感情をいくつかに分類して、それが人間の本質であるという発想を強く批判する。 >> 【書評】『情動はこうしてつくられる』はマーケターにとっても大切な本。の続きを読む
 この本、何がユニークかと言うと「現役の大学学部生による共著」ということで、著者は一橋大学商学部松井ゼミ15期生、で「松井剛編」となっている。松井さんとはとある縁があり、この本もご恵送いただいた。
この本、何がユニークかと言うと「現役の大学学部生による共著」ということで、著者は一橋大学商学部松井ゼミ15期生、で「松井剛編」となっている。松井さんとはとある縁があり、この本もご恵送いただいた。
サブタイトルが「若者はなぜ渋谷だけで馬鹿騒ぎをするのか?」となっていて、「なぜハロウィンか?」という問いと、「なぜ渋谷だけで?」という問いが立てられ、渋谷はもちろん、池袋、川崎と体当たりで取材をしつつ、複層的に解を探している。だから「祝祭論」でもあり「都市論」にもなりそうだが、彼らの専攻はマーケティングの消費者行動論なので、分析のフレームは、その視点で徹底されている。
徹底した現場主義の一方で、準拠集団、アーリーアダプター、アジェンダ設定などのテクニカルタームが飛び交い、ある意味消費者行動論を学びたい初学者にとってはいいテキストにもなるんじゃないかとも思う。
というわけで、「学部生が、よくこれだけ頑張ったな」と思いつつ読んでいて、ふと気づいた。実はこの本は「ハロウィンで騒ぐ若者」を分析しているようでいて、「いまの大学生」のリアルを映し出しているのではないか?
つまり、この本を読んだ人は「騒ぐ若者」を知るだけではなく、「それを冷静に見ている若者」を知ることになる。文化人類学研究の観察記を読んでいるうちに、異文化を知るだけではなく、その観察者の旅行記を読んでいるのと同じようなものなんだろう。
すると、この本は全く別の視点で「今の日本を浮き彫りにする」という、「意図せざる効果」を生み出しているんじゃないだろうか。 >> 【書評】『ジャパニーズハロウィンの謎』が意図せずに描いた”若者”のリアル。の続きを読む